“美らなまち”の活性化を目指して― 沖縄県本部町の挑戦

沖縄県北部に位置し、沖縄美ら海水族館や海洋博公園、桜の名所の八重岳など、美ら海にも美ら山にも恵まれた本部町では、美しい自然を守るプロジェクトを立ち上げ、着実に成果を上げてきました。
新たな取り組みも予定する“美らまち”の現状と今後を本部町企画商工観光課の玉城将吾さんに伺いました。
努力を重ね、美ら海を守る
本部町は2021年度から、「美ら海・美ら山保全プロジェクト」に取り組んでいます。まずはこれまでの道程を玉城さんにお聞きしました。
「取り組み前は、養殖マグロの生け簀にまで赤土が流れ、大きな被害が出ていましたが、対策に力を入れた結果赤土の流出はなくなり、美しいビーチが戻りました」
一方で、本部町の努力だけでは解決できない課題も抱えています。
他国の文字が刻まれたプラスチック製品やブイなどが流れ着く海洋ゴミは、マイクロプラスチックの原因にもなる深刻な問題で、北風が強まる1月から3月にかけて多くなるそうです。
産業廃棄物処理業者への廃棄委託など、より本格的な対策が必要だと玉城さんは感じています。近年問題化したサンゴの白化現象の対策も含め、町では効果的な対策を検討しています。

美しさを増した美ら山
毎年1月中旬に開花する八重岳の寒緋桜。美ら山保全事業の主体となる、このまちの誇りの維持管理について、玉城さんに説明していただきました。
「プロジェクト発足時は年間4名体制で維持管理を行っていましたが、2022年度からは作業員を増員、現在は12~13名で行い、植栽にも力を入れています。事業の成果もあり、2025年は緋寒桜の咲き具合も良好で、県外からのお客様やインバウンドの方も多く集まり、八重岳桜まつりの来場者数は過去最高を記録しました。すべては寄付してくださった方々のおかげです」
本部町では、自然の素晴らしさを教える教育にも力を入れています。琉球大学研究センターの協力による環境教育、海洋教育を各小学校で実施。町内の海岸で見られるウミガメの産卵についての授業では、漂着ゴミが産卵を妨げることを教え、どういった対策が必要かを皆で考え、実際にゴミを拾うといった具体的な対策までを行います。
まちの自然の素晴らしさを理解してもらうことで、進学や就職で一度は町を出ても、いずれ故郷に戻って来てもらいたいという思いをこめた施策でもあります。

寄付企業との連携も
美ら海・美ら山保全プロジェクトには、取材時の2025年2月までの間に、総額1,500万円ほどの寄付が集まりました。寄付企業のほとんどが東京の企業で、業種は設計会社、観光関連企業、IT関連業などとのこと。
寄付企業との関係づくりについて「寄付後には、記者発表や意見交換を行い、2024年度には、4社の代表や役員の方が町に足を運ばれ、視察等もしていただきました。その後、町が抱える課題を共有し、貴重なご意見をいただきました」と玉城さん。“沖縄進出”を前提とした寄附が多かったこともわかったそうで「寄附を受けて終わりではなく、企業と連携しながら地域活性化に取り組んでいきたいと考えています」と寄付企業との連携についてもお教えいただきました。
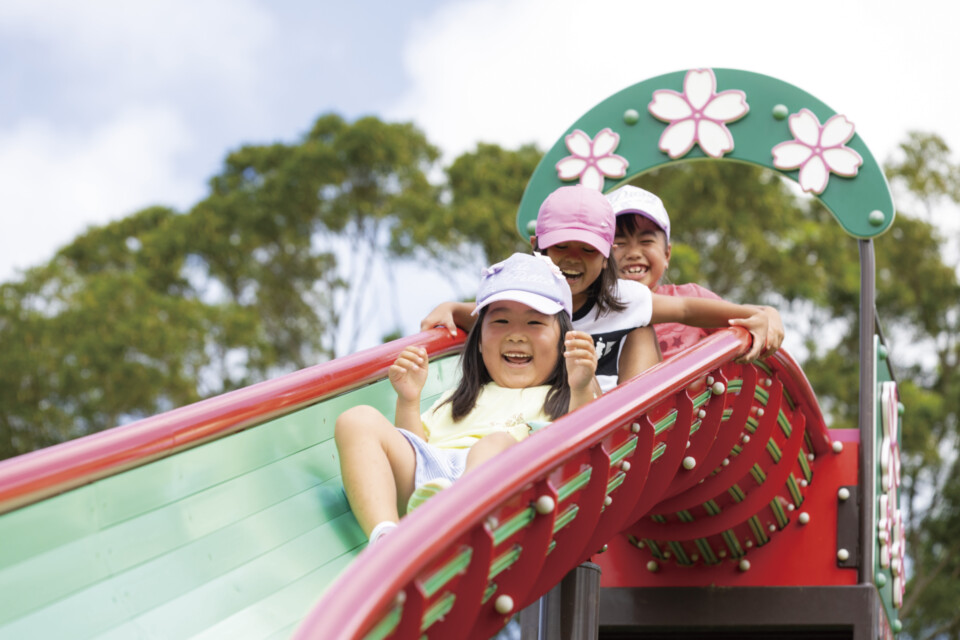
多くの寄付を得るために
現在本部町には、毎年、総額2,000万円ほどの寄付金が集まっています。
ただ、玉城さんは企業版ふるさと納税の担当者として、様々な工夫と目玉になるプロジェクトの新設によって認知度を高め、より多くの事業資金を集めたいという想いを抱いています。
様々な工夫の例としては、寒緋桜が新緑に輝く3月に行われる「新緑まつり」が挙げられます。
イベントでは、桜への感謝と翌年の満開への願いを込めて、小学生が堆肥撒きを行いますが、この様子をメディアに取り上げてもらうことで、寄付の使途について周知し、環境や教育に関心をもつ企業へのPRにつなげたいと考えています。
新たな取り組みとしては、人口減少の解決にも企業版ふるさと納税を活用する可能性があるといいます。町では毎年100人程度人口が減少するなど、対策は急務となっています。
一方で「移住者は多くて転入超過になっていますし、移住希望の問い合わせも多く寄せられている」と玉城さん。
そこで「移住希望者、特に子育て世代の希望に応えられる住居の整備と、子育て支援の拡充を急ぎたい」と玉城さんは続けます。
豊かな本部町の自然環境を守ることは、同時に、多くの人が素晴らしい環境のなかで、豊かに暮らせるまちをつくることにもつながるはずです。
語り手
本部町企画商工観光課
玉城将吾さん
| 自治体 |
沖縄県 本部町 |
|---|
沖縄県 本部町 のプロジェクト一覧



